改善コンサルが読む『ANAのカイゼン』─良かった点、惜しかった点
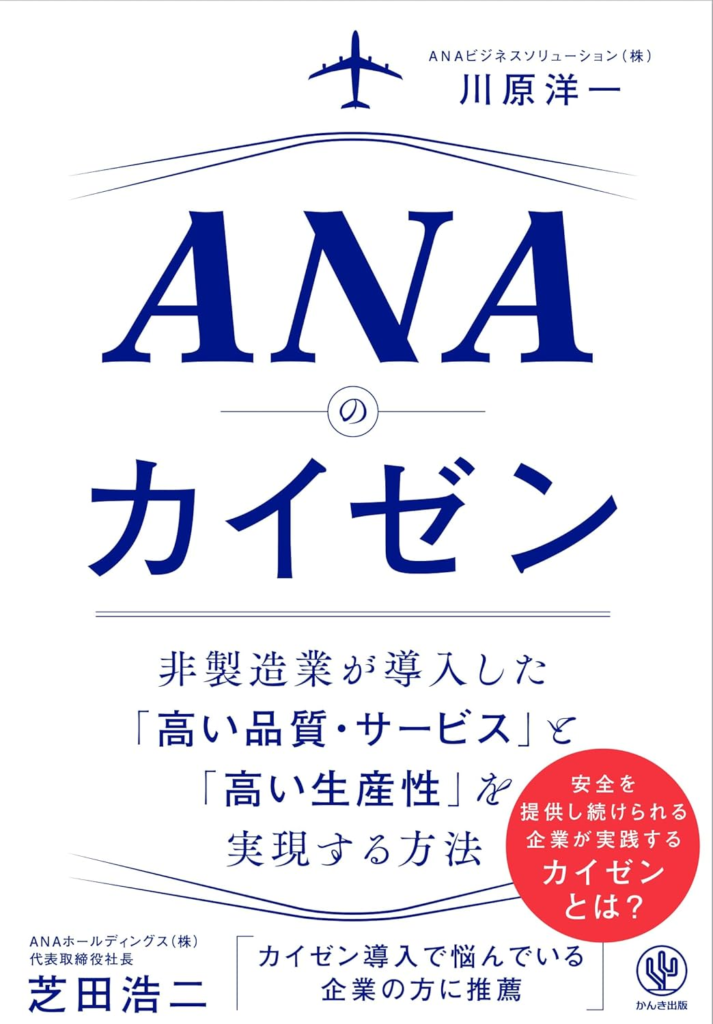
はじめに:沖縄旅行と「ANAのカイゼン」
ハイサイ。4月末に沖縄へ行ってきました。今回の旅ではANAを利用し、機内で『ANAのカイゼン』という本を読んでいました。私は改善コンサルティングを本業としているため、興味深く読了しつつも、いくつか気づいた点もありました。そこで今回は書評(辛口です)と、実際に搭乗して感じた“カイゼンすべき点”についてお話ししたいと思います。
※文中では、本の表記に合わせ「カイゼン」と表記を統一します(改善との違いは本書にて説明されています)。
ANAのカイゼンの概要と良かった点①
この本によると、ANAのカイゼンは2015年に整備部門から始まったとのこと。これは意外でした。私は2003年に大手製造業に入社し、早々に現場カイゼンに関わりましたので、大手企業なら既に当然のようにカイゼン活動を行っているものと思っていたからです。
やや遅いと感じたものの、「今日が自分にとって一番若い日」。やや遅さは感じつつも、このタイミングで始めたこと自体は素晴らしいと思います。
カイゼンは製造業だけのものではない
トヨタ自動車が生み出したカイゼン手法は製造業のイメージが強いですが、本質は「収益のカイゼン」であり、業種や業務内容は問いません。例えば、以下のようにどんな業種でも共通の業務フローを持っています。
| 業種 | フロー |
|---|---|
| 製造業 | 材料仕入れ → 加工・組立 → 検査 → 出荷 |
| 整備業 | 搬入 → 整備 → 検査 → 搬出 |
| 飲食業 | 食材仕入れ → 調理 → 味見 → 提供 |
| 理容業 | 来店 → カット → 検査 → 退店 |
| 病 院 | 入院 → 診断・治療 → 検査* → 退院 |
*治療後の退院可否判断としての検査。
このように、作業の流れが存在する業種であれば、すべてカイゼンの対象となります。
カイゼンの三分類とANAの位置づけ
ANAの取り組みは、いわゆる「自主カイゼン」「QCサークル」に分類されるもので、私はこれを「ボトムアップ型カイゼン」と呼んでいます。
私はカイゼンを以下の3つに分類しています:
- トップダウン型カイゼン:経営・管理層による方針転換や設備投資など
- ボトムアップ型カイゼン:現場主導の改善(QCサークルなど)
- 外部カイゼン:コンサルタントなど第三者の視点によるカイゼン
私は「外部カイゼン」を本業としています。社内に専属担当者を置く場合もありますが、重要なのは「第三者の視点」と「現場との良好な関係構築」、「経営層と現場間でのカイゼンの橋渡し」をすることです。
良かった点②:定量化CAの業務時間削減について
本にはCAの年間業務時間を21,000時間削減したとあります(P4)。ANAのCAは約8,000人(P162)で、稼働率を70%と仮定すると1日あたり約5,600人が勤務していることになります。
- 21,000時間 ÷ 5,600人 ≒ 3.75時間/年/人
- これは月あたり約0.3時間(≒20分)程度になります。
削減効果はあるものの、ばらつきや実感には乏しい数字にも思えます(辛口です)。
ですが、ここで最も大事なことは業務時間が本当に減ったのかどうかを定量的に評価しているという点です。
特に中小企業では、なんとなくとか、どんぶり勘定でカイゼンはしているけど、効果がよくわからないという事例が多いです。
良かった点③:5S活動に関して
整備部門の5S事例が紹介されています。工具を「見える化」して再購入を防止するというのは、どんな企業でも導入しやすく良い事例だと思います。欲を言えば、CAや地上係員などのよりサービス業に近い職種の事例も見たかったです。整備部門は整備工場という言葉があるぐらい、製造業に近い業務フローですので。
なお、私の経験では、多くの企業が5Sを「導入している」と言いますが、実際には2S(整頓・清掃)しかできていない印象です。ボトムアップ型のカイゼンでは5Sの中でも「整理」が特に難しいと感じています。理由は現場レベルでは不要なものを”捨てる”という判断がなかなかできないからです。この件については後日別の記事で詳しく述べたいと思います。
惜しかった点①:紙の削減=カイゼン?の落とし穴
紙の使用枚数を年間4,000万枚から半減した(P104)という事例がありますが、単に紙をタブレットに置き換えただけでは不十分です。
まず5Sの「整理」すなわち、書類自体を廃止・簡素化できないかを徹底的に行わないと、タブレットでも検索の手間が増えてしまいます。これはECRS(Eliminate・Combine・Rearrange・Simplify)の原則に則ったアプローチが望ましいです。
惜しかった点②:搭乗体験で気づいた改善余地
1. 搭乗前の動線案内の不明瞭さ
搭乗の順番を示すGroup 1~3などの看板が見づらく、並ぶ位置に迷う人が多かったです。看板を高くする・横幅を広げる・プラカードを持つなど、視認性の改善が必要です。P108には動線のカイゼンという内容が書かれていますので、是非応用して欲しいです。
2. 優先搭乗アナウンスの不明瞭さ
小さなお子様連れの案内後に小学生くらいの家族も搭乗するようにアナウンスしていました。これは問題ないのですが、親御さんの方が迷っている印象を受けました。該当範囲を明確にアナウンス(例:「小学生以下も対象です」)すればスムーズに案内できます。
3. B787のトイレ“使用中”の表示が見えにくい
B787のトイレ扉上部には緑と赤ライトがあります。遠くから見る分にはわかりやすいのですが、扉の前に行くと気づきにくいです。また、扉のロックの位置にも緑と赤の表示がありますが、この表示が小さく、使用中かわからずに開けようとする人が複数いました。これは色の塗り分けや表示面積を大きくするだけで簡単にカイゼンできます。
使用中にドアノブをガチャガチャされるのは、誰しも嫌ですよね。
この3つの事例で気づいた点は、カイゼンの担当者(いるかどうかはわかりませんが)が現場に出ていないことです。P48には三現主義(現場・現物・現実)が徹底されていないことです。なお、カイゼン担当者が現場を見る際は、担当者・経営者・利用者の3つの視点で見ることが重要であると付け加えておきます。
惜しかった点③:「ありがとう」だけでは足りない評価制度
「褒め合う文化」や「KAIZEN AWARD」は良い取り組みですが、成果が金銭的利益を生むなら還元すべきです。私は経営者に対し、カイゼンによって得た利益の1/3を従業員に還元するよう提案しています。やはりモチベーション維持には「ありがとう」だけでは不十分で、カイゼンの定着は難しいといえます。
惜しかった点④:なぜなぜ分析(P66)は要注意
なぜなぜ分析については本来真因分析に使いますが、対象を“ヒト”にしてしまうとパワハラになってしまいます。これについては過去のブログで戒めています。
本書では Q.エアコンのフィルター詰まったのはなぜか? という例が載っていますが、あえて悪い例と言わざるを得ません。
✕ ヒトに原因を求めるパターン(NG)
→「掃除しなかったから」→「担当者がいないから」→…
○ モノや仕組みに焦点を当てた分析(OK)
→「空気が汚れていたから」→「埃が多かったから」→…
ヒトを責めずにカイゼンするため、私は「Why」ではなく「How」で問題を解決すること推奨しています。
例:「どうすればフィルターが詰まらないようにできるか?」
というように、原因の追及よりもカイゼン方法の追及の方が取り組みやすいです。
まとめ:“良かった点”と“惜しかった点”から見えたANAのカイゼンの可能性
ANAのカイゼン活動は、特定部門の一過性の取り組みではなく、全社的な文化として定着させようとしている点に、大きな価値を感じました。特に、現場主導のボトムアップ型カイゼンをここまで全社に広げた努力は、素直に称賛に値します。現場の知恵を引き出す仕組みを構築し、定着させるには、時間も手間もかかるからです。
一方で、外部の視点から見ると、現場観察の徹底度、カイゼン効果の実感、評価と報酬の制度設計など、さらに伸ばせる余地も多く感じました。これは裏を返せば、ANAのカイゼン活動にはまだまだ成長の余地とポテンシャルがあるということでもあります。
私はANAという企業にとても好感を持っています。旅の安心感や、スタッフのホスピタリティは世界に誇れるレベルです。だからこそ、「もっと良くなる」と信じて辛口な意見も書きました。
これからもANAが日本の誇るサービス企業として、空の安全だけでなく、地上の業務にも“改善文化”を根づかせていくことを期待しています。そして、業界の枠を超えて、製造業以外にもカイゼンの文化が広がっていくきっかけになることを、心から応援していますし、また搭乗します。
OBC 大田ビジネスコミュニティーセンターはプロのコンサルタントによるカイゼン導入も支援しています。


 前の記事へ
前の記事へ